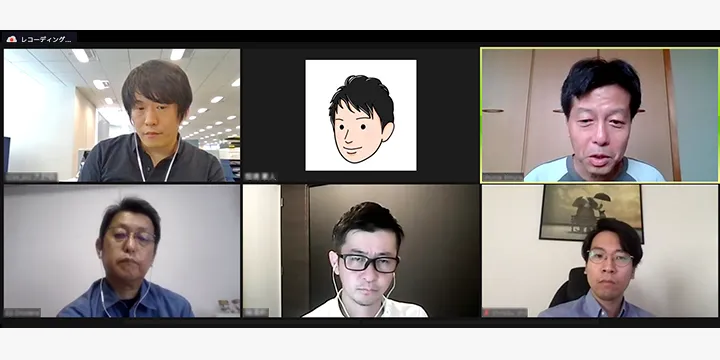BYODは"Bring Your Own Device"を略したもので、日本語では「私物デバイス持ち込み」という意味になります。組織に所属する者(企業の従業員など)が、個人所有のデバイス(スマートフォンやタブレットなど)や個人で利用しているクラウドサービスなどを、組織の許可を得て業務利用することを指します。
BYODの導入と活用に際しては、そのメリットとデメリット、リスクを把握しておく必要があります。
【表】BYODのメリットとデメリット
| メリット |
デメリット |
- 従業員満足度が向上する
- 企業が端末購入などのコストを削減できる
- 業務効率化によって生産性が向上する
- シャドーIT対策になる
|
- 情報セキュリティリスクへの懸念がある
- 私物デバイスに対するサポートやコスト体制が必要になる
- プライベートと業務の境界が不明瞭になり労働状況が把握しづらくなる
|
BYOD導入のメリット
- 企業が端末購入などのコストを削減できる
企業側がデバイスの購入や維持管理のための費用を負担する必要がなくなり、それらにかかるコストを削減できます。 - 業務効率化によって生産性が向上する
従業員にとっては自分の端末を用いることから場所や時間に縛られずに仕事ができるため、業務効率化や生産性の向上につながります。
また企業側から見ると、個人用のデバイスであることから情報セキュリティ部門で一元管理する必要がなく、また操作方法などに対する問い合わせも減少し、本来の業務に注力できることが期待できます。 - シャドーIT対策になる
シャドーITとは「企業が許可していない」IT機器やソフトウェア、クラウドサービスなどを、従業員が独断で導入し業務に利用している状態を指します。BYODは「企業が許可している」従業員の私物デバイスなどの利用になるため、シャドーIT自体の対策になり得ます。
ただし、いずれにせよ私物デバイスを使うことはセキュリティ上のリスクを伴うため、あらかじめBYOD運用のためのルールや体制を整備し、従業員に広く周知したうえで適切にBYODを導入・運用することが大前提となります。
BYODのデメリット
- 情報セキュリティリスクへの懸念がある
BYODの最も懸念される課題はセキュリティおよび情報漏洩の危険性です。私物デバイスを業務に利用することで、データの持ち出し、マルウェアへの感染、端末の盗難や紛失などのリスクが発生します。
- 私物デバイスに対するサポートやコスト体制が必要になる
企業側は、従業員の私物デバイスに対するサポート体制や費用負担が必要になります。プライベートの利用と業務利用で通信費用を分割算定することは難しく、従業員が企業に対して「自分の通信費で業務をさせられている」と不満や不信感をもつかもしれません。私物デバイスを管理し、セキュリティ対策を行うための管理体制やルールを社内であらかじめ整備し、企業側、従業員側が遵守する必要があります。また従業員の金銭的負担と企業側の負担の境界があいまいにならないようルール策定が必要です。 - プライベートと業務の境界が不明瞭になり労働状況が把握しづらくなる
企業側から見ると、従業員の私物の端末のため労働時間の管理が難しくなる可能性があります。従業員側から見ると、いつでも業務連絡の電話やメッセージが届く可能性が高く、プライベートの時間にストレスを感じるおそれがあります。
BYOD導入に際しては、メリットとデメリットを理解した上で適切に導入することが重要です。そのために、以下の点に注意する必要があります。
- セキュリティ対策
情報漏洩などのリスクを防ぐために、セキュリティ対策を徹底する必要があります。 - 運用ルールの策定
私物デバイスの利用方法を明確に定めた運用ルールを策定する必要があります。 - サポート体制
私物デバイスのサポート体制を整備する必要があります。 - 従業員への教育
情報セキュリティに関する従業員教育を継続して実施する必要があります。