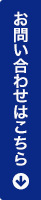インタビュー
マテリアルズ・インフォマティクス 識者インタビュー

ユニバーサル マテリアルズ インキュベーター株式会社
代表取締役パートナー木場祥介氏
「優れた素材・化学企業の育成を通して、日本の技術力を強化し、世界に通用する産業構造を醸成する」というビジョンの下、日本企業やアカデミアが保有する優れた技術・事業と、それらを担う人材の育成に貢献し、事業創出のプラットフォームの提供を目指されている、ユニバーサル マテリアルズ インキュベーター株式会社(UMI)の木場祥介氏を訪問しました。
今回は、内閣府の推進する戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)での取り組みと、素材・化学産業においてどのようにデジタル化のアプローチを浸透させていくかという点について、現状と今後の課題も踏まえてお話いただきます。
最初にあらためて、化学・素材業界における御社の位置づけや活動についてご紹介ください。
ユニバーサル マテリアルズ インキュベーター(UMI)は、2015年に産業革新機構(INCJ)という官民ファンドから独立して設立した、世界でも数少ないマテリアル分野特化型のベンチャーキャピタルです。日本の素材・化学産業で、いかに次の成長の種を育て支援をしていくかを命題としています。つまり、様々な素材・化学産業のベンチャー、スタートアップ、アカデミア、中小・中堅企業、大企業の方々をお繋ぎして、新しい事業をどう生み出していくかを考え、場合に応じてわたしたちの運営ファンドより投資支援をさせていただくというのがUMIのコンセプトです。


ユニバーサル マテリアルズ インキュベーター株式会社
代表取締役パートナー木場祥介氏
SIP(戦略的イノベーション創造プログラム)についてご紹介くださいますか。
内閣府では「サイバー空間とフィジカル空間を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する人間中心の社会」としてSociety 5.0を提唱していますが、これを実現するプログラムである国家プロジェクトがSIPです。これは、科学技術における重要な研究課題を導出し、産学官連携により基礎研究から社会実装までを国として支援するものです。2014年の第一期から5年間隔で行っており、現在は2023年からの第三期ですが、この第三期に掲げられている14の課題の一つが「マテリアル事業化イノベーション・育成エコシステムの構築」ということで、私がPD(プログラムディレクター)を務めております。
また内閣府では、2013年度より毎年度実行してきた科学技術イノベーション総合戦略を抜本的に見直し、2018年度より科学技術の基礎研究から社会実装までの一気通貫の年次戦略として「統合イノベーション戦略」を策定しました。その中で2021年に「マテリアル革新力強化戦略」を出し、その取り組みを産学官が一体的かつ迅速に進め、マテリアルを通じた社会変革を行うことを設定しました。その中には、AI、量子技術、バイオテクノロジー等の新たな技術と高機能材料等のマテリアル技術の融合や、カーボンニュートラル社会の実現などと合わせて、世界最高レベルの研究環境の確立と迅速な社会実装による国際競争力の強化という方針が盛り込まれており、そのアクションプランの中にデータサイエンス技術を活用したデータ駆動型研究開発の促進があります。またそこにはマテリアル DX プラットフォームの整備や、プロセスイノベーションプラットフォームの構築、大学や研究機関に眠っているデータも含めた素材関連データの収集蓄積・利活用の促進なども定義されています。さらに、製造技術データサイエンスの融合ということで、素材発の製造技術にデータサイエンスを融合させて、革新的な製造プロセスの開発を行うという方針が三年前に出されています。これらに基づいてSIPが実行されています。
SIPの最大の目的は、将来ユニコーンとなるマテリアルスタートアップ(以下、「マテリアルユニコーン」)を育てることですが、それを下支えする育成基盤として、エコシステムを推進することもSIPの目標です。これには、スタートアップがシーズから市場に入って事業化し、成長するストーリーを実現するということも含まれています。特にマテリアルはグローバルを見据えた事業化活動が求められる産業領域なので、それを見越して最初から事業ビジネス設計や技術設計、人財育成をしていかなければなりません。これらがエコシステムとなるように、スタートアップに対する支援をサービスや仕組みとして整備をしています。また、マテリアルユニコーンの創出やエコシステム形成を支えるためのソフトインフラ整備や、データ連携基盤技術の確立も課題です。データについては、研究機関や国公立の大学が何十年と構築してきた個々に整備しているデータベース基盤を集約して繋ぎ、スタートアップ側が保有するデータも活用しながら、素材開発や製造プロセスを合理化しビジネスに直結するアプリケーションを作っていくということもSIPで開発しようとしています。また、それをスタートアップが使って事業計画が加速化し、実際にユニコーンになるところまでいくと、今度はアプリケーションの価値を対価としてアカデミア側に還元させて、そこを原資としてさらにアカデミア側のデータ基盤もレベルアップをしていくことができます。この経済的なプラスの循環を作り、最終的にはそのエコシステムとしてアップサイクルに繋げていくことをSIPで目指しています。

では、素材・化学産業の育成と産業構造の醸成という点において、現場ではデジタル活用はどのような状況でしょうか。
これまでの日本の素材・化学系のベンチャーは、機械や装置を扱う方が多い印象で、これらの活用をデジタルの力で加速させて、お客様に対するアプローチや開発プロセスを革新させていこうという状態でした。全体的にはまだ既存のソリューションや、国内で出ているプラットフォームを活用して、自分でソフトウェアを組んで開発に組み込む方が多いです。一方で直近の傾向では、国内の研究やアカデミアの現場で、手が足りないのでデジタルを使うということが活発になりつつあって、それがそのままベンチャー化するので、最初からデジタルツインができていることが結構多くなってきたと思います。そして、マテリアルズ・インフォマティクスを含めたデジタルの力を活用して事業スピードの向上を図ったり、技術開発の手法としてデジタルをうまく運用したりすることもかなり増えています。
中小企業においてはまだまだこれからですが、方向性としてデジタル化は間違いなく進んでいくでしょう。人の採用が難しいことがどんどん顕在化していますが、人手不足でも開発は進めなければなりません。直近のリソース上の課題としてデジタルを使わざるを得ない状況に必ずなるのではないかと思います。そのためには、自分たちで一からシステムを設計してというのは難しいため、外部のパッケージを導入した方が当然スムーズです。今後は中堅企業の方が、デジタル化の取り組みを活性化・活発化してくると感じています。研究開発効率をどれだけ上げていかなければならないか、採用ができないところへどうアプローチすべきかに対して、トップがどの程度コミットメントしているかがとても重要です。日本はこれまで匠の技をどう伝承していくか試行錯誤してきましたが、その技術の継承も危うくなってきていますので、デジタル化で人材をもっと効率よく回していく方向に舵を切らざるを得ない状況になっていると思います。
大企業においては、デジタルツールは各社にとって重要である一方で、評価技術と同じような枠に入れられることが多いように感じます。つまり、研究開発ツールとして組み込まれているというよりは、評価用のいくつかの分析方法の一つとして、デジタルでも確認するという位置づけです。すると、そもそも評価は内部で行われるため、内製化という結論になってしまいます。また、日本企業は、やらないリスクよりやるリスクを叫んでしまいがちで、デジタルツール利用によるデータ漏洩リスクや、データが競合に使われるリスクを回避しようと導入を止めてしまうことが多いのです。でもそれは逆なのです。自分たちがやらなかったら競合が先にやってしまう、その方が大きなリスクだと認識することが大事ではないでしょうか。そこで近年非常に注目度が上がってきているデジタル技術がマテリアルズ・インフォマティクスなのです。マテリアルズ・インフォマティクスは、評価用ではなく研究開発の中に組み込まれるもの、これまで専門の研究者のノウハウに依存して膨大な時間を費やしていた材料設計をAIの力で大幅に効率化するものです。これを活用して早い段階で成果を上げていけるように、過去のやり方や考え方に囚われずにどんどん使ってもらった方が良いと思います。
マテリアルズ・インフォマティクスなどのデジタル導入をスムーズにするために、アドバイスはございますか。
人の手だけで行った場合に開発工数がどのくらいかかり、それに対してデジタルを使ったらどれだけ工数削減やコスト削減が可能になるのか、これが見える情報があればあるほど、社内でその必要性を説明しやすくなります。自分たちの人件費も会社にとっては貴重な投資ですから、デジタルをプラスすることでどこまで効率化できるか、マネジメントならどちらを選ぶかという議論に持ち込めば、導入までの道のりが加速するのではないでしょうか。そして、コストの低い方、効率的な方を選ぶべきだという現場レベルのプラクティスを少しずつ行っていけば、感覚は変化していきます。今はまだツールの機能で何ができるかにばかり注目が集まりますが、それが結果としてどんな効果に結び付くのか、何工数で開発のアウトプットを出せて人件費がどこまで抑えられるのか、そういう考えを当たり前のように身につけていくことが、研究開発効率を上げていくことに繋がるはずです。デジタルの力で世界が変わってしまうかもしれない、他社は同じ発想で先にやってしまうかもしれない、だから早く考えて行動しましょうと声をあげることは、とても大事なことだと思います。それに、日本のようなリソースも資金も限られた中で競争力を担保するためには、デジタルを駆使するやり方はあっていると思います。
マテリアルズ・インフォマティクス導入時の課題や、その対策についてご意見いただけますか。
各社それぞれ違うのですが、データの取り扱いの定義について統一化されていないケースが多いような印象です。どこまでのデータなら出しても大丈夫か、そして大丈夫という定義自体が明確になっておらず、導入したもののデータを使えず、効果が上がらないということもあります。自社のデータを活用する場合の、使われ方・運用の仕方は、正確に理解をしておく必要があります。アルゴリズムがよくわからないということも聞きますが、まずは機械学習の構造や、データサイエンスの一般論的な考え方を押さえておくといいでしょう。そして、安全なデータの使い方や、どの精度でアウトプットされて、それをどう評価するかなども理解しておくことが大事です。
また、日本人はより技術的な情報を求めるため、深入りした腑に落ちるような説明があるとより良いですし、それを補完するためにも、例えば初心者のための基礎的なマテリアルズ・インフォマティクスの本がもっと出てくるといいですね。データエンジニアリングの座学的なところをまずは理解して、その先のビジネスに繋げるためのデータサイエンスを、マネジメントの方にも浸透させていくことが重要になっていくと思います。最近はデータサイエンティストの資格を取る方も増えてきていますが、ただ資格保有者を増やすのではなく、データ駆動で何を効率化してどんなアウトプットを出したいかというマネジメントの強い意志が背景にあることが大事です。パッケージという点では、例えばCitrine Platformのように直感的にクラウド利用できるようなグローバルで利用されているプラットフォームがあるわけですから、日本においてもそういうものの活用に早く着手できることが他から何歩も先をリードすることに繋がると思います。そして、自社で全部賄えない部分については、SCSKさんのようなソフトウェアベンダーが伴走して教育やサポートを行うことを期待しています。

素材・化学産業が目指す姿について、ご意見をいただけますか。
データ駆動開発やデータ収集は手段であって、目的ではありません。日本ではまだまだデータ駆動開発やデータ収集自体が目的化しているケースが目立つのですが、データは陳腐化していきます。ですから、新しいモデルと新しいデータ、そして未来を創造する事業シナリオを念頭においた上で、様々なデータ駆動開発ツールを使いこなしていくことが重要ではないかと思います。様々なところで物事がデジタル化して、人間が考える思考よりも速いスピードで世の中が動いている中では、変わらない課題や将来の課題を目標にし、その目標に対して会社としてどんな製品やソリューションを充てるべきなのかを真剣に議論しなくてはなりません。そして、そのための開発項目が何であって、それはどうやったら誰よりも早く実現ができるかを考えたときに、それはデジタルの力や社外の力を使うべきという発想を持つことが大事だと思うのです。なんとなく使いましょうではなく、しっかりと目的意識を持ってどこの部分を加速化させたいかを意識すること、そしてデジタルの力を借りてどこよりも速く、競争力を担保するという考え方、これを日本の素材化学産業がもっと持つようになっていくと、あるべき方向に進むように思います。
素材・化学産業は、今や日本の製造業のGDPにおいて、1/3以上を占める基幹産業となっています。すでに国際競争力と技術や設備などの豊富な資源がある企業各社と、オンリー1またはナンバー1を生み出し新規事業創出を担う可能性のあるベンチャーが連携しながら共に大きく成長し、日本の技術力の強化や世界に通用する産業構造の醸成に繋がればと考えています。
投資家という立場から、多くの企業の育成と事業創出にご尽力されてきた木場様のお話は、デジタル化への向き合い方を考える上で大変貴重な内容であったと思います。この度は、SCSKのインタビューにご協力くださいまして、どうもありがとうございました。
記事制作(取材日:2024年4月2日): SCSK株式会社 デジタルエンジニアリング事業本部 藤田航介, 星雅人, 近藤晶子
ユニバーサル マテリアルズ インキュベーター株式会社ホームページ
SCSK株式会社 デジタルエンジニアリング事業本部 E-mail: eng-sales@scsk.jp Tel: 03-5859-3012
- 本文に記載の会社名、部署名、製品名などの名称は、取材日時点のものです。
- SCSK株式会社に事前の承諾を得ることなく、本記事の全部または一部を使用(複製・改ざん・頒布・送信・上映)することを禁止します。
また、ダウンロード、プリントアウトされた複製物を、不特定または多数の人へ送信・配布することはできません。
- ※掲載されている製品、会社名、サービス名、ロゴマークなどはすべて各社の商標または登録商標です。
製品・サービスに関する
お問い合わせ・資料請求
ご質問、ご相談、お見積もりなど
お気軽にお問い合わせください。
プロダクト営業部
E-mail:eng-sales@scsk.jp お問い合わせフォーム